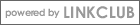December 29, 2006
�裳��ꥢ������ţ����ӡݣ�
���ӡݣ����ʱ�ο�
���������Υ��ꥯ�����롦�ѥ�����ˤ��ֲ����θ����פιֵ��ˤϡ���ӥ��������������롢�쥤�ꥢ�������ե��֥쥪������ȥ˥��˴ޤᡢ�轵��˳ؤμ��Ȥ��������ʤ����ȥȡ���ꥫ�λѤ⤢�ä���
���轵�Τ��졢�ʤ���ä��������
����®��ӥ����ȥȤ��䤤�ͤ�롣
�֤��䡢���Ǥ�ʤ��衣��
�ֺǶᡢ�ȥå�������Ĵ�Ұ����ߤ������ʡ���
���ե��֥쥪���ɷ⤹�롣
�ּ��ȡ��Ϥޤ�衩��
���ȥȤϲ�����̴�ǡ��쥸�������������
�����Ĥ�Τ褦�ˡ������ʽ��ꡢ�֥饷�������إ�Ф����ꥯ�������������������褦����ˡ�ǿ�ɽ��Ÿ�����롣
��¨�����ԥ��륫�ǥ����ˤ⤤���Ρդ�ή����ˡ�ˤ��������٤Ȥϡ���������Ѥˤ�뤽��Ȥϰۼ���ʪ�Ȥʤ�ޤ����ͤϡ���ưʪ�俢ʪ�ˤ�Ǥ����������⤽�⼫�ʼ���ǽ�Ϥ������Ƥ��ޤ������ε�ǽ����Ū�˰����夲��������µ���������Τ���������Ѥˤ������Ǥ���
���ԥ��륫�ǥ����ˤ⤤���ΡդΡ������٤ϡ������оݤμ��ʼ���ǽ�Ϥˤ�餺���̤��Ϥ��äƼ�����Ԥ��ޤ��������Ϥλ����ˡإ��ɤ�©�٤ȸƤ�Ǥ��ޤ�����
�������դ�ϡ�������٤ι��ǯ�Ԥʤ�оQŪ�����Ƥ��������Ȥ������ȤʤΤ�������
���ȥȤ�Ǯ���ˤ���Ƭ�˶������ꥯ������θ��դ�ϳ�餵����α��Ƥ�����
�������ͻҤ��ܤ�ª���Ƥ����쥤�ꥢ�ϡ��٤��ʤΥ�ӥ��ˤ��ä��������
�֤ɤ������Τ����顩�������������٤������㤦���
�֤������ʡ����ˤʤ�ʡġġ���
�ֲ����˼���դ���Ƥ����ʤ������顣��
�����λ����ȥ�ȥ�ȶ��Ť�á����������������ȡ��֥饷�����������礭�ʥ�����ܤǤ�������ˤ�Ǥ��롣
�֤����٤á���
��³���ϸ�Ǥ͡���
����ͤϤ���ʾ��ˤޤ�ʤ��͡����Ȥ���ǰ���뤳�Ȥˤ�����
�ֻվ������Ρ������٤ȳ���Ū�ʽѤ��Ȥ߹�碌�������٤ʼ��Ť�Ԥ����Ȥϲ�ǽ�Ǥ��礦������
�����λ��Τ���˹ͤ��Ƥ���������ꤲ�����Ƥߤ��ӥ���
�֤����Ǥ��͡ġĺ��ޤǤ��Τ褦�ʻ����ߤ��Ԥ�;�ꤤ�ޤ������������ϸ�����Ǥ��礦����Ѥθ��̤ϡ������оݤ˶ᤱ��жᤤ�ۤɤ���礭�ʸ��Ϥ����뤳�Ȥ�����ޤ����㤨�С��ڳ��������ɽ�Ф����������ˡ������٤νѤ���к��ޤǰʾ�˲�������ޤ뤫���Τ�ޤ���͡���
����ʬ��ȯ�ۤ�����Ū����ǤϤʤ��Ȥ�������ʬ���ꡢ��ӥ��Ͼ���������������
�������˥֥饷��������������ä��롣
�ֿ��ޤ��Ѥ��뤳�Ȥǡ����˸��̤������ޤ��衣�㤨�С����졣��
������顢�ʹ֤η�����ʪ�κ��Τ褦��ʪ����Ф��֥饷������
�֥ޥ�ɥ饴��Ȥ����ƥ���������©���뿢ʪ���ۤϡ���ˡ�ο��ޤȤ������˹⤤ǽ�Ϥ�ͭ���Ƥ��ޤ����ġĤ���Ϥ������Ϸ��Ǥ����ɤ͡���
������ؤΥ������ѡ��ȤȤ����Τ���֥饷�����ϡ�ø����³������
��â���������������Ǽ��˹Ԥ����ʤ�ƻפ�ʤ��褦�ˡ������μ褹��Τϻ���ζȤǤ������ʤ������ȼ���ޤ�����⡢��ʪ�ϼ�ˤ������Ϥ���ޤ��������ͭ���Ƥ���Ȥ�����ġġԲ��۳��ɡդΥ���������������Ĺ���餤�Ǥ��礦������
�֤ؤ������������ʤʤ������
����ò������夲���Τϡ��ȥȤ��ä���
�����Ȥ�����ꡢ��ӥ��ȥե��֥쥪�������ƥ쥤�ꥢ�϶����˻Ĥ껨�̤˶����Ƥ������ȥȤϤȸ����С��ȤäȤȴ�ɼˤ˵��ä��褦��������ˤϡ����ΥȥȤ˴ؤ��뤳�Ȥ������롣
��ή�Ф��Ѥ��ʡġļ��Ȥܤ뤫�Ȼפ��С������ʤϴ���Ū�ʻ��ޤǿ��餤�դ��Ƥ���������
�֥ȥå�������Ĵ�Ҥ���Ȥ��Ƥ���ߤ��������ʡ��ޤ��������ˤȤäƤϤ��ΤޤޤǤ��Ƥ��줿�顢ͭ���ɡ���
���ե��֥쥪�ϡ���ʬ�Υ���������Ӥ�Ƥ��Ƥ���褦����
�֤����顢�����˼���դ���Ƥ����ʤ������顣��
�ֲ����ˤäơ���
�֤����������ޤǤϡġ��㤨�С����ۤȤ�����
���쥤�ꥢ�ϥȥȤ��Ѳ��ˤ��Ƥ���褦������������ʬ����С���ʬ�ǡּ��šפ�ܤ��Ƥ����褦�Ȥ����פäƤ���Τ��⤷��ʤ���
�֤��㡢���١���������ܿͤ�ľ��ʹ���Ƥߤ뤫������Ǻ�ߤ�����Τ����Τ�ʤ������쥤�ꥢ�θ����Ȥ��ꡢ�����˼���դ���Ƥ���Τ����Τ�ʤ�����
����괺�������ͤȤ⡢����ҤοȤ�Ƥ��Ƥ���ΤϳΤ��ʤ褦����
�֤Ȥ����ǡġıʱ��̿���äƤ����Τϲ�ǽ�ʤΤ�����
����ӥ���������Ѥ��롣����ϥ�ӥ����ȤΥơ��ޤǤ⤢�ä���
�֤����͡���ñ�ʤΤ��ΤäƤ��ޤ����ɡ���
�֤�����
���Ͼ��������Ǥ�������ꤷ�ʤ��Ȥ�����
�����䡢����ϥ����ब�㤦��
�֤���ʤ���ä���ġġ���ǯ�˽��������������¡��ư�����ʤ��Ȥ��������������
�������̡�褬�ġġ�
�֤ϤϤϡ����㡢�������廊���ɤ�ǭ���ɤä�����äƤΤϡ���
���Τ��˺Ф���ʤ����ɡ�
���ȡ��ĥå������ʤ����̤ϡ����θ��³������
09:28:29 |
hastur |
comments(0) |
TrackBacks
December 18, 2006
�裳��ꥢ������ţ����ӡݣ�
���¤νִ֡�(Il Momento della V���rit���)
���ر�Ĺ��������Ĺ���Υ��֥��������Ⱦ��˹������ر���Ǥϡ��͡����Բ���ư�������������褦�ˤʤä��褿���ر�����˲����Ʋ����ο�ʪ���ƥ��������ԲIJ�ʹ�ư������ʤ��ء�������Ĺ����ɼ�����¤��Ӥ��̡ܶ������Ƥ������ݴɤ���Բ��۳��ɡդγ���Ĺ���ڥ�����Ĺ�����ġġ�
��������桢�ԥ��륫�ǥ����ˤ⤤���ΡդǤ⺣�ޤǤˤʤ������������Ƥ��롣Ʊ���ˣ��ͤ�ν��꤬�������鵢�Ԥ������Σ��ͤȤ⤬��̩�ᤤ����ư���Ƥ��롣
���̤����ƿ��¤ϲ���ˤ���Τ���������
���ӡݣ����������
�֤Ǥϡ�������äƤ�����Τϡ���
����������ˡ��ƥ��ե饹�ȡ��ѥ饱�륹��������Ĺ�Τ��郎�줿����������
���������˱������Τϡ����쥤���������å����ä���
�֤Ϥ�����������館�Ƥ��ޤ�������
�����쥤�����������ȡ��ȥå���ɤ������դ����ä��Ƥ��⤤�Ƥ��������ȤǤϤʤ����Ƥ��⤤�Ƥ����Τ���
�֤ۤ����ʤ��ʤ�������Τ��ä��Ρ���
���ƥ��ե饹�Ȥ���ľ����Ҥ�˫��롣
�����쥤����ä��Τϡ��ȥå���ɤ������ѤΡ֥��������ʲ��Ρˡפ��ä�������̾���̤ꡢ�Ƥ��������Ƥ�������ο���̿���ä���������Ū�ˤ����Ω����ʪ���ä���
�֤��ࡣɾ�����ͤ���ʡ��Ĥ��Ƥ���������
�����������ʤ��顢�����ʻ�˲���������ƥ��ե饹�ȡ��⤷������ȡ����쥤��´�Ȥ���ʤä��Τ��⤷��ʤ���
�����������Ȥ˻��ä�����ϻ��ä��Ƥ��뤬������ʤ��Ƥ��ʤ��ä���ӥ���������������ϡ������ͻҤ��ۤäƸ��Ƥ������������ʤ��ä���
�����Ȥν�λ�塢���쥤�ȥ�ӥ��ϥƥ��ե饹�Ȥ˵ͤ��ä���
�֥ѥ饱�륹���ա����ǥ�����ȥ��������ˤĤ��ơ����ä�����ΤǤ�������
���ƥ��ե饹�ȤϤ������ˡ�������������ư��������
�֤������ġĵ��Ť������Ρ������ǤϤ��Ȥޤ�������ͤȤ���ѯ�����������褦�ˡ���
����Ϥꡢ������ͤˤϲ�����̩�����롣�ο��ᤤ����Τ��������쥤�ȥ�ӥ��϶�͡��˸����ä���
���ƥ��ե饹�Ȥ������Ϥ���äȤ���ưʪ��Τ褦���ä��������μ�Ϥɤä���ȰػҤ˺¤äƤ��ꡢ����˵��ˤϥ��ǥ������塼�ǥ�Ƚ��꤬Ω�äƤ�����
�֤��ơ��ɤΤ褦�ʷ�����ã��������ʹ�����Ƥ�餪�����Ρ���
����˸������Τϥ��쥤���ä���
�֤��Ρ����ǥ�����ȥ����餵��äơ������κ�ä�����̿�ǤϤʤ��Ǥ�������
�֤����ˤ⡪���ɤ����㡢�ɤ����褸������������������Ф��Τ��ᤫ�ä��Τ��ġġ���
���ƥ��ե饹�ȤϾ����μ�ǡ�Ƭ��ݥ�ݥ��ߤ��ʤ��餽�����ͤ�����
�֤������ʤ��顢��������ϡ���
�������䤤�ˤϥ�ӥ�����������
�ֲ��η���������Ƥʻ��������λ����ä��ʤ��������������Ǥ��Խ�ʬ�Ǥ��礦������
�֤थ��ή�Ф˷���ޤǤϵ�¤����ä��襤���������äϡġ�Ŭ���˶����Ƥ����Ф褫�ä����Ρ���
�֡ġIJ����λ��϶����Ƥ��äƤʤ��ä��Τǡ���������ޤ���Ǥ����衣��
�����ǥ��������ܤ���
�֤��㤬�����̤���ο����ϣ������Ȥ����Ȥ�������Ρ���
���ƥ��ե饹�Ȥ��Ե�̣�ʾФߤ��⤫�٤롣
�֤Ǥϡ����̤���ˤ�äƤ�餤�����������롣���ǥ��ȥ���������Τ�Ф�ʤ��褦�ˡ���äƤ��졣ѯ�Ϥ��Ρ��ر��Ϥޤäư����δ����ͷ��Υۥ�륹�ʿͷ��ο���̿�˺���������ȯɽ������Ĺ����ĩ��Ĥ�ꤸ�㡣���ΰ٤ˤ����̤οʹ֤Ⱥ����äƤ�Ф�ʤ����٤Υۥ�륹�Ȥ��������ͤФʤ��
�����ΰ٤ˤϸ��֤ϱ����̤��ͤФʤ��
��������Ĥ�Σ������̤����õ�����Ƥ�����
08:42:45 |
hastur |
comments(0) |
TrackBacks
December 06, 2006
�裲��ꥢ������ţ����ӡݣ�
���ӡݣ���ͼ�ʤ�
������ʤ���ʤǥ��ǥ��β����뤳�Ȥˤʤä���ӥ����ä���������äƤ��륢�ǥ��˴ؤ��Ƥޤ����������������ʬ����٤��ؤ�Ʊ���γʤΥ��ǥ�������ô���Ǥߤ�Ȱ��ͤ˷ڤ��Τ���
�������������Ȥ⤢�ꡢ���Ū���Ϥ˼����Τʤ���ӥ��Ǥ��ݷޤǤ�ƻ���ϸ�������ΤǤϤʤ��ä������ʤʤ�С����餫����ˡ��ȤäƳڤ�Ȥ�������
���٥åɤ˥��ǥ�������ȡ��ڤ��ǻ���Ԥ����Ǥ��Ȥ������ڤ��Ϸ�Τ褦����
���������٤���ˡ��ܤ������Ф餯�ͻҤ롣
�����ǥ����ܤ�Фޤ����ˤϡ��������褦�Ȥ��Ƥ�����
�ַ������Ť��Ƥ��줿��Ǥ��͡����꤬�Ȥ��������ޤ�����ӥ�������
���٥åɤ���Ⱦ�Ȥ��������Ҥ٤륢�ǥ���
�֤������ݷ�Ѱ��Ȥ��������Τ��Ȥǡ������ꡢ���ǥ������ʹ���������Ȥ�����ΤǤ�������������Ǥ�������
�֤������ʤ�ʤ�ȡ���
���ޤ���Ĵ��ͥ��ʤ��Τ��������������Ǥ�Фߤ��⤫�١��������֤���
�ֲ����ǤϤɤ�ʻ��Ƥ����ΤǤ����������������äȤ����ä��餪ʹ�����ꤤ�����ΤǤ�����
�������������鿧�δ�ǡ���ӥ��ϿҤͤ롣
�֤����äǤ����ġĺ���ޤ����͡����Ԥ˱����뤳�ȤϽ��褽���ˤ���ޤ���͡��դ˸��ߤᤵ��Ƥ����Ǥ��衣��
�֥ѥ饱�륹���դˡ��Ǥ�������
���轵����������Ǥ�줿�Τ�Ʊ��Ÿ����������Ǥϡ��ȥ�ӥ����ڤ�����Ѥ��Ƥߤ���
�֤Ǥϡ��վ��Τ��ȤȤ�������������äȤ����ꤤ���ޤ�����
�֤���ʤ�ġĻվ����ѥ饱�륹���դ��Τ���ȤƤ�ͥ�줿��ѻդǤ�������ѻդȤ��Ƥ����ǤϤʤ����ʹ�Ū�ˤ������餷�����Ǥ���������ϳر�Ĺ�Ȥʤ�졢���ꥢ�����˱ɤ�⤿�餹���ȤǤ��礦����
�������������ӥ��ˤϡ��ѿ͡٤Ȥ����Ǥ�ʤ�����ľ��ҤȤʤ�ȸ�����٤�㤦�Τ���������
��������⡢�ܤ�ϯ�ɤ����褦��ø���Ȥ�����Ĵ���ڤ��ؤ�ä��Τˡ��������ä������Τ�����
�ֳ�������ϡ��ä��礭�ʽ������ʤ�ʿ���ޡ��Ȥ�����ΤǤ������䤿����������Ժ���ä��ߤ����ǡ�������̾���Τ줿��ѻդ�ФƤ��ޤ���
���Ѥ��ʤ���Ĵ��³���륢�ǥ���
�����������Ȥ��ʤ��������ġġ�
�֤��á��⤦ͼ���Ǥ���������ɼˤλŻ�������Τǡ�����Ǽ��餷�ޤ��衣��
�����ǥ��Ϥդ�Ĥ��ʤ���⡢�ݷ�ФƹԤä���
������Ȥۤ�Ʊ������쥤�ϼ�ʬ�������ǡغ��ʡ٤λž夲�ˤ����äƤ�����
�����ڡ����졢�ȥå���������
��Ʊ���γ����������롣�Բ��۳��ɡդΥ��������ȥ롦��������Υ��������쥤���鸫������ǯ���ǡ��������Ρ��٤β��ۤ���ޤ����Ȥ������οͤǤ��롣
�֤��줬�ȥå��˸�����ʤ顢�ܴۤ����ȸ��äƤ⤤���Ǥ��͡���
���Բ��۳��ɡդοʹ֤����ְ㤦���餤�ʤ�С���ɸ��ã����줿�ȸ����롣���쥤�ϥƥ��ե饹�ȤΥȥå���ɤ��ͤˡ���ʬ�ʤ�Υȥå���ɤ����ϤäƤ����Τ���
����ǽ�ϥƥ��ե饹�ȤΤ������Ѥ��ʤ��������������쥤�Τ���ϡ���ʪ�Υȥå���Ʊ���礭���Ƥ�����
�֤���ϻ���Ϥä�����̿�ΤǤ��衣���ۤǤϤ���ޤ���
�֤ؤ������ԥ��륫�ǥ����դäƤΤϴ��Ѥ��ͤ�������ʤ��ޤ��Ϥ���������ۤ˸����Ʋ��ۤˤ��餺��������
�����������ȥ뤬��ò������夲�롣�����ƿ��ָ塢�۹ͤ��Ϥ�롣
�֤��������������ġĤ��β�ǽ����ͭ���ʡ���
�֡���
����ͤǾ����Ǽ�����Ƥ��륶�������ȥ���ܤˡ����쥤�Ͻгݤ�������롣
�֤���äȽгݤ��Ƥ��ޤ��衣ľ���˵��äƤ��ޤ�����
�����쥤�ϼ�˴�ñ����ˡ���ơ�����Υȥå���ɤ�������夲�����Ԥ���ϡ��å���Υȥå��֤������
������ޤ��ۤ�Ʊ�����ɼˤο�˼�ˤϥ쥤�ꥢ���ʤ�Ǥ�����
�֥����餵�ɤ������Τ�����ġġ���
���쥤�ꥢ�ϡ������ϥ����餬�������֤�ʹ���ơ��虜�虜�ִꤷ�Ƥ������褿�Τ���
���������������ԤäƤ����Υ����餬�Ѥ��ʤ���
���ѡ��������ä�ʹ�����ȻפäƤ��Τˡġġ���
������ʻ���֤��֤����äƤ���ȡ�ï������˼�����äƤ�����
������ȡ����Ȥ˥����������֤鲼���Ƥ��롢���Ӥξ�������
�֤��졩�������顢�ޤ���Ƥʤ��Ρ������������褿�Τˡ���
�����γʹ���������Ĥ�꤫���顩
���쥤�ꥢ�Ϥ���ʻ���פä��������ˤϤ��ʤ��ä�������ϡԷ���ԡե����������ꥹ�η�������Υ��ꥷ������
�֤ޤ���Ƥʤ��ߤ����衣�ġĤǡ��������äơ���
�֤����������ϥǥ�������������ɤͤá���
�����������ȡ����ꥷ���Ͼ���˺�Ȥ�Ϥ���ϼ��Ǥ���������äƤ��ơ��ե롼����⻳�Τ褦���Ѥ߾夲�롣
�������Ƥɤ�������äƤ����Τ������̤�ɹ�ξ�Ǻ���������
�ֲ���äƤ�Ρ���
�֥ߥ륯�Хʥʥե�åڤ衣��̣�������Ǥ��礦����
��̾��������ʹ���гΤ�����̣�������������������̤�Ⱦü�ǤϤʤ���
�����Ф餯����Ȼ��ξ�ˡ��ե롼�Ĥ������餳������ͤ��ɤ��ä�ɹ�λ�������夬�ä���ɸ����300mm��
�֤����ơ���������ĺ�ʴ����ˤ���͡��ФƤ��뤫���顣�Ǥ⡢ñ����ĺ�ʰ�ͤǴ����ˤ���ʤ����ˤ餷���ʤ����͡������å�����Ȥ�����ʣ���ͤǿ��٤���ˡ��ӥС������������ǵٷƤ���ˤʤ�Ƽ�ƻ��á���
�����ꥷ���Ϥ��������餱������ɹ����Ĥ���Ω����äƤ��ä���
������ʰ�̣�ǿ�˼�ε����������ä��������롣
�����Ф餯����ȡ���äȥ����餬�Ѥ�����
���٤�Ƥ��ߤޤ��ġĤ���á����Ǥ���������ϡ���
�������ʤ�ɹ�����ܤ�������ˤ����ä��Ƥߤ��륤���顣
�֤��ä������ꥷ������äƤ����ޤ������ߥ륯�Хʥʥե�åڡ��餷���Ǥ��衣��
�֡ġĤ��졢ñ����ĺ����͡������Ǥ����͡ġġ���
���褯����ȥ�����δ鿧�ϰ������������������Էʰ��ݤ������Τ��������Ϥ�����ؤ�����Ĵ���������ܤ����Υե�åڤΤ��������Τ�ʤ�����
�֤���Ĵ�����Ϥ�ޤ��礦������
��������ޤˡ����Ĥ����٤�ͼ����꤬���Ϥ��줿���쥤�ꥢ�ϼ���ˤʤ�ʤ��褦�ˡ�����Ĺ����ȱ�����ǤޤȤ��������ζ�ȱ�ϡ���Ȥ�ȥߥǥ������Ĺ���ʤΤǤ��Τޤޤ���
�����ư�����ʤ��顢�쥤�ꥢ�ϥ�������ä������롣
�֥����餵��ϡ������ǽ��Ԥ��Ƥ�����Ǥ���͡������λ����á�ʹ�����Ƥ��������衣��
�֥쥤�ꥢ�������ʹ���Ƥ�̵�̤�������
�����Ĥδ֤ˤ��ظ�ˤϥ�ӥ���������ɹ���λ�ĺ�դ��Ĥޤ߿������Ƥ��롣
�֤ɤ��������ȤǤ�������ӥ�����
�ֲ������äϻվ��˸��ߤᤵ��Ƥ��롣�����Ǥ���͡������餵��
����ӥ��θ��դ�̵�������������顣
���쥤�ꥢ�Ͼ������ä��ꤷ����
�֤���ʡġIJ����ˤ���ɤ��������٤νѤ����ä����ɤ�����ʹ���Ƥߤ����ä��Τˡ���
�֤���ʤ�ΤϤʤ��衣��
���ޤ��̤�����ʹ�����������Ĥδ֤ˤ���ӥ����ظ�˥ȥȤ�Ω�äƤ��롣
�֡ԥ��륫�ǥ����ˤ⤤���Ρդ���ˡ�ϡ������٤˴ؤ��ƤϺǾ�̤Τ�Τʤ���������ˤϤ���ʾ�Ρ������٤ʤ��¸�ߤ��ʤ��衣�ġĤĤޤꡢ�������㼣���ʤ�������µ��⡢���ꥢ������ѻդʤ鼣����äƤ��Ȥ�����
������ʻ����Τ�ʤ��Τ����Ȥ������٤Ǥޤ���Ω�Ƥ�ȥȡ����Τ����פĤ��Ƥ���褦�ˤ⸫���롣
���Τ��˥��ꥯ���μ��ȤǤϡ�������ä�ʹ�������Ǥ⡢�ºݤ˲����˹Ԥä���Τʤ�С�̤�Τ���Ѥʤ���ΤäƤ����ǽ��������Ϥ��������פ����쥤�ꥢ�ϥ�������ä�ʹ�����Ȥ����Τ���
�֤��ΡġIJ������äʤ�С��˥��饦�����ǥ���������ˬ�ͤ����������Ȼפ��ޤ��衩��
��������Ϥ������������ʤ������˰���դ��ä�����
�����������쥤�ȥ��������ȥ��������
�����쥤����Υȥå���ɤ��ȥå������ʶ����ޤ��Ƶ��𤷤Ƥ�����
�֤��졩�����ä��Υȥå���ɤ��ϡ���
�֤���Ȥ����ˡ��͡���
���˥�˥䤷�ʤ��������륰�쥤�������ա��վ��˻��Ƥ��ޤä��Τ��⤷��ʤ���
�֤����ꤵ���������ʹ�������Ȥʤ���������
�����������ȥ뤬�̤��ä롣
�ִ�ɼˤ������ʡ��٤β��ۤ����ˤ��Ƥ������äƤΤ��ΤäƤ�����������ޤ�������ϲ��ȡԷ���ԡդβ����������Τ�����ޤ���������ɤ�������Ȥ��̤ˡ���ˤʤ�ȳ����餦�����ʹ�����Ƥ������äƤ�����
�������äʤ饰�쥤��ʹ�������äƤ�����
�ֳΤ��ġĵ���¢�ˤ������顢�Ȥ����äǤ����͡���
������¢�ˤϡ���ɼˤ��龯��Υ�줿�Ȥ����ˤ���ƶ���ǡ�����ï�����դ��ʤ���������¢�ˤȤ��Ƥϴ��˻Ȥ��Ƥ��ʤ����������˻��ޤǤ�ƻ�ˤϲ��ۤ�ä��褯�и����롣����¢�ˤޤǤ�ƻ�ϡش�����ƻ�٤Ȥ���¯�Τ��դ����Ƥ��롣
�֤����ʤ���衣���줬���٤�ر��˲���ȴ�Ϣ�����뤫�ɤ�����ʬ����ʤ�������ɤͤ�����
�����������ȥ�Ͼ������Τ�����ˡ���̣��Ф��Ƥ���ߤ�������
�֤�����ġ�ͼ�����ޤ����ʡ���
��ͼ���Ϥۤܡ��������Ƥ�����
�֤��㡢���졢��Ʋ�˱���Ǥ�����������ӥ����Ϥ��Υե�åڤ���äƹԤäƤ�����������
�֤������������ġġ�
���ȥȤ�쥤�ꥢ�ϡ��ѥ����䥵����ӽФ��Ƥ��롣������ϡ��̤��ѻ�������Τǡפȸ����Ĥ�����˼�����äƹԤäƤ��ޤä���
���������ʹ���Ƥ����������ȤΤ��ä���ӥ��ϡ����ȱ��Ҥ�����ۤ��ǿ�˼���ˤ�����
08:37:44 |
hastur |
comments(0) |
TrackBacks